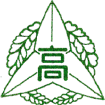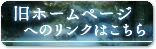◆稲葉真弓さん講演会 ~私の津島高校 裏街道をゆく~
2013.9.3(火)於 津島市文化会館
文学賞の誕生の意義
皆さん、こんにちは。文学の世界は曖昧模糊としていて、心の世界を描くものですから、なかなか文学というのは形をはっきり説明できない。はっきりと説明できないんだけど、人の心の中の魂に触れるようなジャンルであり、新たに皆さんのところの津島高校で文学賞ができるということは、私にとって本当にうれしいことなのです。
これからの時代というのは、むしろそういうはっきりとしないもの、心の問題というのがとても大事になっていくのではないか。こういう岐路に立った危うい時代に、文学が新たにこういう形で生まれていくということは、何とも言いようのない胸一杯になるような思いがしております。
今日の演題に「私の津島高校 裏街道をゆく」と書いてありますけど、別に津島高校が「裏街道」ということではなくてですね、私の人生は、津島高校を出発点として、なんだか文学というものと格闘するための人生であった。その格闘が、なかなか表面的なところに出てこなくて、裏の暗い部分ばかりを歩いてきた。その暗い部分が、文学をやっていくのにとても役に立った、というようなことをお話したいと思っています。
文学との出会い①
私が文学に出会ったのは、実にこの津島高校の3年間だったんですね。小学校の高学年から中学、高校とずっと私にとって文学というのはとても大事なもので、ただその頃は、文学ということは意識していなかった。むしろ物語、物語を読むこと、物語に触れること、そういうことが私にとっては趣味だったんですね。それでいろんなところに小さな作品を書いては、中学生の頃から投稿していた。だから雑誌の投稿魔だったんです。あっちに投稿し、こっちに投稿してチョコレートの景品をもらったりして、とても自分にとっては居心地のいい場所であった。
津島高校では、演劇部に属していました。当時の演劇部は、非常に優秀な先生がいらして、しかも優秀な先輩もいらした。そういう先輩たちに引っ張られて演劇部でお芝居をしていたんですが。その頃に出会ったチェーホフの『桜の園』とか、テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』とか、そういう戯曲を介した表現に非常に興味を持ったんです。その頃は高校演劇祭とかコンクールに私たちも出て、みんなで見に行ったりしましたが、他の学校がたまたまテネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』という作品を取り上げていました。
この作品はたいへん美しい作品で、引きこもりの少女ローラと、ジミーだったかな、お兄ちゃんと、お母さんと三人、お父さんは行商のような仕事をしていて出て行ったきり帰ってこない、三人の母子家庭で暮らしている。お兄ちゃんは引きこもりのローラのために尽力して、一人の少年、自分の友達を連れてきてローラに紹介するが、彼にはすでに恋人がいて、ローラの恋はつぶれるわけですね。お兄ちゃんは、お母さんとの軋轢(あつれき)だとかローラの落胆、悲しみを全部背中にしょって、彼も家を出てしまう。それから何年か経ってからの回想のシーンがありまして、舞台に照明がパッと当たると、家を出てから何年も何年も経っている現在の青年の一人語りが始まるんです。「僕は月よりも遠い場所に来てしまった。月は遠いけれども、その月よりも遠い場所に僕は来てしまった。」って。それは時間のことを言っているのですが、それと家族を捨てた悲しみというものが、月よりも遠い場所として彼の中に刻み込まれているわけですね。
その「月よりも遠い場所」という一言が私の心にグサッときて、それで、私はその言葉を悲しみの言葉として受け取らなかったんですね。人生というものは、そういうふうに私たちを月よりも遠い場所へと運んでいってくれる。その到着した場所が、たとえば青年の到着した悲しみの世界なのか、あるいは別の喜びの世界なのか、それは人によってたぶん違うものになるはずである、というふうに思って、私は、その月よりも遠い場所を、喜びの場所に変えたい、私も月よりも遠い場所に行きましょう、というふうにそのとき思ったんです。そのように『ガラスの動物園』は非常に印象に残ってグサッときて、自分の人生がどうなるのかわからないけれども、その「月よりも遠い場所」に行きたい、と思った、それがある意味文学であったわけです。
文学との出会い②
もうひとつ津島高校での文学との出会いがあります。
多くの文学者は、あの頃にドストエフスキーを読みましたとか、あの頃に『レ・ミゼラブル』を読んで感動しましたとか、そういう大作を読んで感動するんですよね。感動したということを回想としてよくインタビューの中で話をしているんですけれども、私の場合は、教科書だったの。皆は教科書なんて見るのもいやと思ってるかもしれないけども、現代国語の教科書の中に、西脇順三郎さんの詩が載っていたんです。その詩は、たった三行か四行で、わけのわからない詩なんですけど、西脇順三郎の代表作『Ambarvalia』というモダニズムの詩集として有名な詩集があるんですけれども、その中に「ギリシャ的抒情詩」というタイトルのついた「天気」というタイトルのついた、短い三行の詩が載っていた。
覆された宝石のやうな朝
何人(なんぴと)か戸口にて誰かとささやく
それは神の生誕の日。
という三行なんです。この詩は一回読んだだけではわかりません。「覆された宝石のやうな朝」、この朝がたいへん美しいことはわかる。晴れやかで、ああ美しい朝だなあ、とこの一行を読むと思う。そこに「何人(なんぴと)か戸口にて誰かとささやく」、誰が来たのかわからない。とにかく誰かが誰かというふうに訪れた人に対してささやく。「それは神の生誕の日」というふうに書かれているんですね。
私は宗教とかいうものを全く持っていません。何かに取り憑かれた記憶もなければ、宗教的なものに惹かれたこともなかった。けれどもこの「神」とはいったい何であろうか。最初は、教科書の中でこんな詩、読んだことないよね、何かこんな訳わかんない詩を、なんで教科書に載せるの、って思ったんですけども、何回か読んでいくと、この詩の中にある美しい情景、朝の晴れやかさ、その中に誰かが訪れてくる。その誰かというのは誰かわからないんだけども、それを迎える人にとっては神のような人である。あるいはその光かもしれない。窓から差し込む光が「覆された宝石のやう」にきらめいて、それが窓から差し込んで、それが部屋の中にいる人に、何人(なんぴと)か、あなたは誰?というふうにささやく。その光が、訪問者を受け入れる、あるいは光か何かを受け入れる、私にとって「神」のように思えた、というような解釈もできるわけ。
私は解釈がいろいろできる不思議な詩を、とにかく手放せなくなってしまった。もう常に常に気になって気になってしようがないんですね。西脇順三郎さんて人は一体どういう人なんでしょう、と自分で調べてみたら、モダニズムの詩人だというふうに書かれておりました。モダニズムの詩人、モダニズムっていうのがよくわからない。モダンな詩の、昭和の抒情詩とはちょっと違う、新しいスタイルの詩を当時の人たちはみんな求めていて、それが西脇さんにとって新しい表現になっていったんだけれども、『ambarvalia』という詩が非常な評判を呼んだんですね。それは人々を引きつけて、新しい詩人たちがどんどんどんどんこういう詩を書き始めた。私もそのモダニズムの詩にとても惹かれてしまって、名古屋の同人誌に出入りするようになった。詩を書きたくて。それから私は詩を書くようになったので、高校時代から詩に馴染んでいたんですね。
「津島高校と私」というタイトルの中には、まさに文学との出会いというのがあって、その文学がひとつはチェーホフなどの戯曲であり、ひとつは新しい詩のスタイルであったんです。この新しい詩のスタイルというのが、後に私の小説の文体とか、小説の内容とかに非常に影響を与えてくれる。高校生のときに出会ったものというのは、スポーツにしろ、こういう文学的なものにしろ、思想にしろ、今は何の役にも立たない、わからないまま通り過ぎてしまうようなことが、後に何かの形で花開く、あるいは知らない間に蓄積されていく。今の時間というのは、長い長い年月を薄く薄く堆積させながらできあがっている。今の年月の豊かさというものは、私たちが小学、中学、高校、大学というところを経てきた時間の地層とまさに重なっていくわけですね。だから今の私は赤ちゃんの時代からの地層が成し得ているんです。その今の私はまた何年か後の地層、社会人になったときの地層、あるいは中年になったときの地層という重なり合いの中に人生というものが豊かになり、あるいは辛さもその中に含まれるかもしれないけど、ふくらんでいって、それで私たちの一生というのは誰かに受け継がれて、また新しい地層がそこにできていく。地層から地層への受け渡しがなされていく、そういうすばらしい土台みたいなところに今私たちは生きている。皆さんは10代の土台、私は60代の土台ですが、生きるという意味においては、今この地層の一カ所にいる、今ここにいるということが大事なことである。私の大地の何層目かに津島高校があったのですよ。だから私は自分の文学のことを考えたときに、あそこで演劇部をやっててよかったなあとか、あの教科書に出会えてよかったなあとか、あの「天気」という短いたった三行の詩に出会えてよかったなあ、ということを時々思うんですね。
脈々と流れる私の中の津島高校
そういう文学との出会いがありまして、同人誌時代、投稿生活が始まって、そのときすでに小説家になりたい、作家になりたいと決めていました。20代のはじめの頃ですけれども、私はあまりにも本を読みすぎて、学校の勉強が嫌いで嫌いで、とにかく学校に行きたくない。高校生の頃は本当にひどい成績でね、特に理数系がだめでね、国語はよかったんですよ、現代国語だけはよかったの。後は全部ダメなの。理数系は全部赤点。本当にひどい成績だった。だから今こうして皆さんの前で偉そうなことを言っている自分が、本当に恥ずかしいのだけれど、学校の勉強がだめでも、人生というのは大丈夫なんだよ、ということはちょっと言いたいんです。人生というのは、別のところでふくらんでいって、あの子はこんなふうになったんだわ、と先生たちがびっくりしてくれたりして。
私の旧姓は平野と言って、結婚して稲葉になりましたけど、相手は津島高校の一つ上の先輩だったんです。だから同時期の同世代の人と結婚したんですね。彼とはとっても仲良しで、しかも演劇部の先輩で。結婚して東京に出て、彼が会社員になって、大阪に転勤になって、いろいろあって有為転変の中で、だんだん距離が離れていって、結局別れちゃったんですね。別れたけど、けんか別れをしたわけではないので、稲葉という名前だけは使わせてね、っていって使っています。。
あるとき、あまりにも学校の成績が悪く進級できるかどうかというときに、橋本富慈先生っていう、とっても格好のいい、女性の英語の先生で、いつもお着物で学校にいらした、とてもきりっとした素敵な先生だった、その先生が、「平野さん、どうしたの?体調でも悪いの?」と声をかけてくださった。私は涙がこぼれそうになって、もうだめかもしれないと思ったけど、先生は「でも元気そうだから、頑張れるわね。」って言ってくださり、私は口から出任せに、「先生、ごめんなさい。私、神経衰弱です。」なんて言っちゃったりして、まあ無事に津島高校は卒業することができました。そういうふうに後ろから支えてくださったささやかな言葉に感謝しています。成績が悪いまま卒業していったわけですが、このあたりも私にとってはあまり表沙汰にしたくない、恥ずかしい裏の顔なんですけど、今思えば、なんだか出来の悪い自分もいたんだ。だから人生において出来の悪いときもあれば、出来のいいときもある、という開き直りというか、地に足がついてあまり動揺しなくて済むような意識は生まれたのかなあ、とは思うんですけどもね。
私は先輩と結婚したわけだが、実はうちの母と父も津島高校で出会っているんです。昔の形の学校だったときに、母が理科室の助手として働いていて、父は英語を教えていました。英語の先生と理科室の助手の女の子とが出会って恋が生まれて、父と母は結婚することになったので、津島高校は、父と母との時代から私の恋愛、結婚とずっと繋がってきた、まさに脈々としたルーツみたいところも含まれているわけです。だからとてもこういう珍しいケースはあまりないのではないかと思うんですね。父と母との出会いのあたりから、津島高校は私の中で特殊な位置を占めている、といえるのかもしれませんね。
東京での下積み生活―貧乏が教えてくれたもの
上京後に投稿少女はもう少し進化していくわけで、どんどんどんどん書きたくて書きたくてしようがなくて、いろんなものを書いて、でもどこに投稿しても必ずボツになってしまう。でもめげずに書き続けられたのは、書くことが好きだったから。いろんなものを書き続けているうちに、ひとつひっかかり、ふたつ新人賞にひっかかりというふうに、なんとなく二次審査、三次審査あたりまでいけるようになったんですね。そうなると、あっ大丈夫なんだ、二次審査までいけた、次は第三次までいってみよう、と思って書くでしょ。だから書くことが自分にとってすごく大事なことになっていった。
でも若いですから夫の収入が少なく、共働きして、夜中に帰ってきて、それから夜中に書く。だから睡眠時間がほとんどなく、気がつくと朝の四時とか五時。たいへんたいへんって言って寝て、六時頃起きてまた会社に行く、というような生活をしておりました。高校時代と同じで、どうも私の性格らしいんだけど、とにかく書くことに夢中になってしまっていました。夫は大阪に転勤になり、「君、一緒に来る?」って言われたときに、「いやっ!私、東京にいる。」って言って、だんだん距離が離れていった。別にけんか別れではないけれど、別れることになってしまった。それから一人暮らしが始まったんです。
このときの一人暮らしは、もうとても素晴らしかった。この貧乏っていったら、本当に素晴らしかった。皆さんにここで貧乏を自慢するのは馬鹿みたいだけれども、風呂敷かぶって歩いていたの、私。日本の風呂敷って結構模様などおしゃれで、大判で安い、シルクなんか使ってあるものをボロ市なんかで買ってきて、真ん中に丸い穴を開けて、その穴をかがって、すぽんとかぶって、要するにずた袋ですよね。肘のあたりをちょっと閉じたりして、風呂敷は真四角なんだけれども、前垂れを三角にすると後ろに三角がいって、結構おしゃれなんですよ。その模様さえ選べば、風呂敷もおしゃれなものになるということがわかって、風呂敷をせっせせっせとミシンで縫って、洋服として着ていた。
お米は母が愛知県から送ってくれて、おうちではこの頃食べていたもののなんと素晴らしいこと!まず、ひじきですね。袋に入っていると小さいけれど、水に戻すとこんなに大きくなるのね。コーヤドーフも小さいけど、水に戻すとこれも大きくなるのね。みんな膨れるもの。わかめもそう。膨れるものをとにかく毎日食べてた。ひじきは甘辛く煮て、お揚げとか入れて、それをお弁当にご飯と一緒に詰めて、ご飯の上にふりかけをのせて、卵焼き作って、必ずそうしてお弁当を持って行った。
貧乏な生活は2、3年くらい続いた。ちょっとお金があるときは、チーズを買ってひじきをグラタン風に焼いたり、卵とじ風みたいにアレンジしてみたりして。コーヤドーフも中にいろいろ挟んでそれを焼いたりして。こうした洋服や食べ物の貧乏生活における体験、自分の工夫が、小説を書くのに生きたのである。作り方さえ、発想さえ変えれば、物事というのはこんなに豊かになるのだし、こんなにおもしろいものだ。小説の中に工夫する、作りを変えればいいんだ、ということを私は発見したんです。貧乏生活でも私はちっとも落ち込まなかった。今日は何を作ろう、次は何を作ろう、って楽しくって楽しくってしようがなかった。『風と共に去りぬ』の中で、戦争でなんにもなくなったときに、主人公が緑色のベルベッドのカーテンをドレスに仕立てるシーンがあったんですよ。そのドレスに仕立てるシーンがとても素敵で、私も真似してみましょうと思って、古いカーテンをきれいに洗って、それをドレスにして着て歩いた。それを見てみんなが、「稲葉さん、それどうやって作るの?」「稲葉さん、それどうやって組み合わせたの?」って言って、珍しがって、逆にすごくおしゃれだ、なんて言ってくれるわけね。風呂敷だって、「えっ、風呂敷なの?風呂敷がこんな風になるの?!」って、みんなが褒めてくれたんです。もう得意で得意で、褒めてくれたことがまた自信になった。あっ、私は生きられる、と思ったし、貧乏がこんなに素敵なこととは思わなかった。そのときは切り詰めて切り詰めて大変だったけど、非常におもしろかったですね。
転機―覆面作家
貧乏生活をしていると知った編集者が、「稲葉さん、これは稲葉さんが目指すものではないけれども、あるアニメがあって、大変人気なので、ノベライズをしたいんだけれども、文章力があって、ちゃんとした文学の勉強をした人に書いてもらいたい。新人のポンと出た人には渡したくない作品なので、稲葉さん、このアニメーションをノベライズ、小説化しませんか。」って言ってくれた。私は貧乏ですから、くる仕事は全部断らなかった。「やります、何でもやります。」と言って、そのノベライズのお仕事を引き受け、アニメーションをテープに起こして、それでノベライズをやっていくわけです。
そうしたらそのノベライズがなんと何十万部と売れちゃった。文庫本で20何冊か書くことになって、一冊が五万部くらい売れましたから、総計で百万部くらい売れちゃった。私はそのときペンネームを使っていたので、稲葉真弓という名前は言わなかった。名前は伏せたまま、覆面作家としてやっていた。けれどもすごくお金になった。貧乏生活から急にお金がどんどん入ってきてびっくりしちゃって。引き受けていなかったら、私はどうなっていたことか、なんて今は思いますね。
純文学への挑戦―小説家としての独り立ち
窮地に立って、とにかく一ヶ月に一冊書く。すごい勢いで書いちゃう。それがまた自分に自信になったんですね。私、書けるんじゃないの!こんなに書けるんだから、純文学の方だって絶対書ける、やりましょう、と思った。ノベライズのお仕事はバブルがはじけるとだんだん下火になっていって、そのお仕事は幕引きということになったときに、はじめて私は、自分の書きたいものを渾身の力をかけて書きましょう、と思ったんですね。
それで書いたのが『エンドレス・ワルツ』というモデル小説だった。麻薬におぼれていく若者のカップル、実在の作家と実在のサックス奏者との恋愛小説ですけれども、これは本当に自分が生きられなかった人生で、麻薬におぼれる女性主人公は鈴木いづみといって、作家で、全集も出ています。鈴木いづみの青春小説はものすごく人気があったんですね。鈴木いづみの相手となった人が、阿部薫というジャズメンだった。阿部薫は薬をやっている。鈴木いづみは睡眠薬の常習者。その二人が出会って、ある日、阿部薫が「俺を本当に愛しているんだったら、おまえはどんなことだってできるだろう。足の小指の一本ぐらい切れるだろう。」って言ったら、鈴木いづみは平然として、「あら、切れるわよ。」って言って本当に足の小指の先っぽを切っちゃった。もう酔っぱらってぐっちゃぐちゃになって、よれよれになって、それでも二人は別れることができなかったの。
暴力あり、薬物による幻覚あり、もうぐちゃぐちゃなんだけれども、彼らの青春は輝いていたんですね。こうした輝く青春があるんだ、ということを私は初めて知った。彼らの生は、そういう形でしか燃焼できなかった。若い人の中にはそういう形でしか燃焼できない人がいるんですよね。たとえば暴力でしか燃焼できない、人をいじめることによってしか自分を生かすことができない、燃焼できない。もちろん自分の中ではこんなことしてはいけないと思っているのだけれども、そうしないと自分の中のうっぷんが晴れないから、つい人を殴ったり、いじめたりしてしまう。いじめられるほうは冗談じゃない、すごい傷ついて大変なことになってしまうんだけど、そういう負の世界、マイナスの世界でしか生きられない人がいるんです。
そのマイナスの輝きというものが、人生には必ずあるんですね。しかも青春の中にも負の輝きというものがあるんです。私は、負の輝きをとにかく汲み上げたかった。彼らの中にある負が、彼らを生かしている。これは一体なんだ。私が生きられなかった生を生きてる。もちろん私は薬をやりたいと思ったことは一回もないし、ジャズメンと出会ったことも一回もない。ジャズは好きでしたけど、音楽は全くだめ。音痴だしハーモニカ一つ吹けない。鈴木いづみは本当は妊娠したくなかったんだけれども、阿部薫の子を産んだ。その後、阿部薫と鈴木いづみは二人とも死ぬ。最初に、阿部薫が薬物の過剰摂取で死にます。死にたくない、死にたくないと言いながら死んでいきます。それなら睡眠薬を飲まなければいいのだけれども、負の輝きに取り憑かれているから睡眠薬は離せなかった。どんどんどんどんお酒を飲んでいるうちに、睡眠薬をガリガリかじって、何錠飲んでいるのかわからなくなって、結局は99錠、一瓶に1錠だけ残っていたそうですけど、それで亡くなった。その後鈴木いづみは遺児と二人で、売れない小説を書いて、貧乏して暮らしていたんですけれども、肺結核か何か見つかって、人生
に絶望するんですね。人生に絶望して二人で二段ベッドに寝ていたんです。上に子どもが寝ていて、下に鈴木いづみが寝ていたんだけど、ある夜、鈴木いづみはベッドの上の板にストッキングを引っかけて、それで首をつって死にました。
そういう生は嫌だよ、という切り捨て方もあるけど、彼らが残したものというのは、そこにしかない、その人にしかできない何かがある、ということ。非常に不快な、とても褒められたような生き方ではないけれども、ある意味、そこに物語、人生の物語、阿部薫の人生の物語、鈴木いづみの人生の物語、それぞれがあって、それが摩擦をしながら、ひとつの青春物語を作っていく。そういう話を『エンドレス・ワルツ』で書いたわけです。そうしたらそれがたまたま割と大きな賞(女流文学賞)をいただいて、それから私は一応小説家として独り立ちをしていくことになったんですけれども。
負の世界こそが人間の世界
本当にどこでどういうものに出会うかわからない。私は、鈴木いづみと阿部薫を知っていたわけではない。ある日、本屋さんへ行ったら、真っ黒な薄い本があって、タイトルも何も付いてないんですよ。ただ真っ黒、表紙が真っ黒、お棺(かん)みたい。いろんな明るい表紙の本が並んでいる中に、ポツンとその真っ黒なのがあって、なぜかまるで棺(ひつぎ)みたいではないか、と思ったんです。生き生きした本がある中に、お棺があるみたいに死の世界がポッと黒く、真っ黒くあった。
それを手にしたら、阿部薫の人生がそこに書かれていて、鈴木いづみとの関係も書かれていて、しかもそれが私と同世代の人の話だった。こんな人たちがいたの?!、ともうびっくり仰天でした。正直言うと、私は嫉妬しました。私はこんなに平穏な生活で生きてきたけど、この人たちはなんと激しい人生を生きてきたのだろう。こんなに過激な、ラジカルな、激しい人生は、私には生きられなかったなあ、と思って。もちろん私は夫と別れたり、いろいろあったけれど、それは自分にとっては激しいものではなくて、そうせざるを得ない自然の流れの中で生きてきたことであって、しかしこの人たちは、60年代70年代のラジカルな東京の文化、たとえばそのときに寺山修司がいたり、いろんな過激なものがいっぱいあった、それらを全部取り込んで、彼らは東京という街で全身で生きていた。
その全身で生きるということが、当時の文化の負の部分を引き受けることだったんですね。それが私にとっては痛ましくも嫉妬に駆られる。痛ましいんだけど、ああ悔しい、私はこんな人生を送れなかったなあ、と思って、それでその人たちの人生をなぞってみたい、と思って書いた。だから私の中には、鈴木いづみや阿部薫に通じる負の世界があった。もしなかったとすれば、接点がなかったら、おそらく書かなかったと思う。私の中にはそういう負の世界を理解したい、あるいは触れたい、そういう欲望があってね。負の世界こそが人間の世界ではないか、というようなことをどこかで思っているところがあるんです。ただ清く正しく生きるだけが人生の意味ではなくって、負を引き受けていくことも一つの人生の意味である、というようなことを鈴木いづみたちから学んだ。
だから今の私の中には、負の人生の檻(おり)のようなものがあって、次にどのような人と出会うかわからないんですが、できれば清く正しく真っ直ぐに生きた人よりも、どこかゆがんで、しかし人を捉えて放さない、すごいねっていう人と出会いたい、と思っているんですね。私は人間をどこで信じるかというと、きれいだとか、優しいとかそういう表面はどうでもいいの。とにかくその人がどう生きているか、そこへ突っ込んでいきたい。中身だけがその人を語れる、ということなんです。格好がいいとか、見栄えがいいとかではなくて、割とダサイけど、いいとこあるよね、っていう人。ダササというものが人間の本質で、人間ってダサクって汚いもの、そんなきれいなものじゃない、と私は思っています。きれいなものではないんだけど、そこにその人らしい輝きがある、その人しか出せない輝きがある、そういうものを拾っていきたい、出会いたい、すくい上げたい、一緒にいたい、という気持ちがすごく強いんですね。だからたぶん小説家になったんだろうと思うんですよ。小説家というのは、人間の弱い部分とか汚い部分とかうまくいかない部分とか、一生懸命そこを乗り越えていく、あるいはそれを引き受けていく、そういう人間を多く書きますよね。真っ直ぐな潔癖なものに励まされるというよりは、むしろ弱きものに励まされる、というようなところが人にはあるんですね。弱きものが必死になって生きている、そういう姿に打たれる。それで自分も頑張ろう、というふうに思う。私はたくさんの友達がおりますけれども、そんなに立派な人はおりません。もちろん同世代の人で非常に活躍していて、仲良しの人もいっぱいいますけども、一番仲がいい人は、何かどこか間が抜けているというか、なんか弱々しいというか、しかし芯の部分を見ると強い。そういう表面では見えないものを持っている人が好きですね。
文学から学んだこと、文学にできること
言葉との出会いは、様々な出来事の中で、皆さんの中にこれからきっと生まれると思うんですね。小さきもの、弱きもの、そういうものと一緒に生きていくということを、きっと発見すると思います。是非是非発見していただきたいと思います。津島高校での生活を十分楽しんで、そこで発見したものがどういうふうに大きくなっていくのか楽しみに、自分の力を信じて生きていっていただきたいと思います。
静かに聴いてくださって、ありがとうございました。裏街道の話は、もうちょっとしたかったけれど、貧乏生活とか、負の世界に出会ったこととか、私の裏街道のひとつだと思って理解してください。どうもありがとう。